
日本や海外で活躍する女性起業家・経営者10人!成功例や起業に向いている女性の特徴とは?
開業・起業したい女性必見!女性起業家の成功例から学ぼう 「起業」と聞くと「男性がやる仕事」とイメージをする方もいるかもしれません。日本は、ほかの国と比べるとまだまだ男性社会の色が強い国です。しかし、起業をして成功を収めた女性は多くいます。 そこで、今回は日本における女性起業家の現状や起業に向いている女性の特徴を解説していきます。また、日本のみならず海外でも活躍している日本の女性起業家も紹介していきますので、起業を目指している、どのような起業家がいるのか知りたい方は参考にしてください。 また、「創業手帳woman」では、女性起業家インタビューだけでなく、女性起業家向けの補助金・助成金なども掲載しています。無料でのご提供ですので、ぜひお気軽にご利用ください。 女性起業家の現状 まずは、日本における女性起業家の現状について解説していきます。 女性起業家は増加している 日本は海外と比較するとまだまだ女性起業家の数は少ない傾向ですが、年々増加しています。東京商工リサーチによる第12回「全国女性社長調査」によると、2023年の女性社長は全国に61万2,224人いることがわかりました。調査をスタートした2010年では女性起業家が21万2,153人だったため、13年の間に約3倍も増えたことがわかります。 また、女性起業家を都道府県別に見てみると、大都市を中心に多くいることがわかります。最も少なかった県は、島根県で2,158人です。 女性起業家が増えた理由としては、インターネットの普及が考えられます。 例えば、アパレル業界となると店舗を構える必要があると考える方もいるでしょう。しかし、近年ではネットショップが普及しパソコン上で取引きが行えることから、趣味や好きなものを取り扱う分野で起業する女性が増えてきています。インターネットがあれば女性でも気軽に事業をはじめられるため、女性の起業家進出を後押ししたと推測されます。 産業別ではサービス業での起業が多い 次に、女性起業家の数を産業別に見ていきます。 産業 女性社長数 構成比 サービス業他 30万840人 49.14% 不動産業…
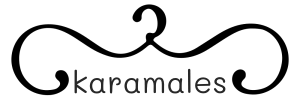










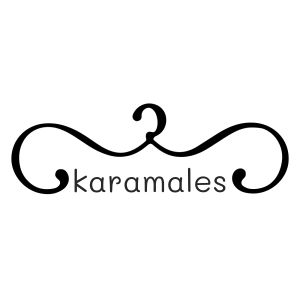
 Alden Cargo Shorts
Alden Cargo Shorts